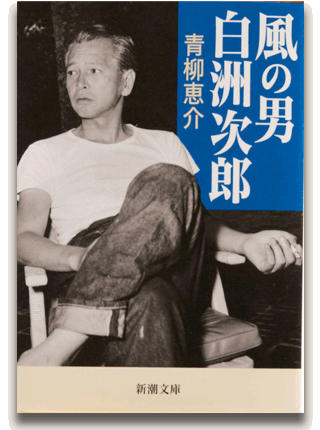武相荘の沿革

私たちは、〔太平洋戦争開戦の〕二年ほど前から、東京の郊外に田圃と畑のついた農家を探していた。食料は目に見えて少くなっており、戦争がはじまれば食べものを確保しておくのが一番必要なことだと思っていたのである。
その頃、タチさん〔幼少より正子についていたお手伝いさん〕の親戚におまわりさんがいて、南多摩郡鶴川村の駐在所につとめていたが、彼は至って好人物で、秋は栗拾いに、春は苺(いちご)狩と筍(たけのこ)掘りに、子供たちを誘ってくれた。万葉集の東歌(あずまうた)にも詠まれている「多摩の横山」の丘陵ぞいに、茅葺(かやぶ)きの農家が点在するのどかな農村で、戦争が近いことなどどこにも感じられない。おまわりさんは、もし郊外に家を探しているならぜひ鶴川村へ来るようにとしきりに誘った。
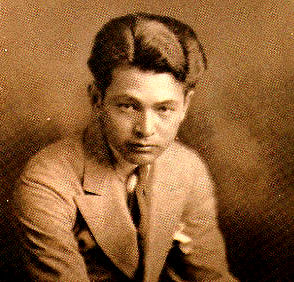
折も折、次郎がつとめていた日産系の会社をやめたので、退職金が入った。たしか一万円か、二万円足らずであった。そのまま持っていればどうせ私たちのことだからなしくずしに使ってしまう。それなら、土地でも買っておいた方がいいということで、おまわりさんの世話で鶴川の付近を見て歩いていた。売家はいくらでもあったが、いずれも帯に短かく襷(たすき)に長しで、探すだけに一年以上もかかってしまった。

ある日の帰り途(みち)に、こんもりした山懐にいかにも住みよさそうな農家を発見した。駅からもそんなに遠くはない。あんなところがいいな、住んでみたいなあと、ひとり言のように呟(つぶや)くと、おまわりさんは私の帰ったあとで、直ちに交渉してくれた。
それは咄嗟の思いつきにすぎなかったが、縁というのは不思議なもので、話はトントン拍子にきまり、翌月からもう修理にかかることとなった。
その家には年老いた夫婦が、奥の暗い六畳間に、息をひそめるようにして住んでいた。息子さんはどこか遠くへ出稼ぎに行っているとかで、ぜんぜん構って貰えなかったらしい。そんな哀れな人たちを、追い出すようなことはしてくれるなと、おまわりさんにはくれぐれも頼んでおいたが、彼らはむしろ喜んでおり、せめて電車の見えるところに住みたいと、快くゆずって貰えたのは倖(しあわ)せなことであった。
その老人たちが住んでいた北向きの部屋が、今は私の書斎になっているが、農家の人々にとっては、いわば「姨捨山(うばすてやま)」のような一隅ではなかったであろうか。彼らばかりでなく、四、五代前の老人たちも、皆この部屋で命を終えたかと思うと、見知らぬ人々であったとはいえ、ある種の感慨を覚えずにはいられない。五十年も住んでいれば、私にとっても何か「結界」のような感じがして、書斎へ入る度に身の引締まる思いがするのである。

そんな風であったから、家の中は荒れ放題だった。茅茸屋根は雨洩(あまも)りがしていたし、床も腐って踏みぬくというあんばいである。買ってはみたもののそのままでは住めなかったが、さすがに骨組だけはしっかりしており、大黒柱や梁(はり)などは見事なもので、それだけで私たちは満足した。
それは昭和十五年のことで、若者たちはみな召集されて村には年老いた大工が一人残っているだけだったが、戦争がはじまった後でも、すぐ空襲がはじまるわけではなし、ゆっくり修理をすればいいと思っていた。で、私どもは水道町の家から鶴川へときどき通っていたが、そうしたある日のこと、突然東京にアメリカの艦載機が現れて、何発か爆弾を落して行った。空襲警報は鳴る。兵隊さんは駆けつける。隣組の人たちが右往左往する。私はどうしていいか判(わか)らず、子供たちを抱いてぼんやり眺めていたが、飛行機は数発爆弾を落しただけであっさり引上げてしまった。そのあとから黒煙が上るのを見ていると、とてもこうしてはいられないと思い、直ちに鶴川村へ引越すことに決心した。なまじヨーロッパの状勢を知っていただけに、臆病になっていたのと、そうでなくても私ども夫婦はせっかちだったのである。
「鶴川村へ移る」/『白洲正子自伝』所収